|
 |
| 蚤虱馬の尿する枕もと (尿前の関) |
|
3日前に日帰りで「奥の細道ツアー」に参加し、栃木県那須岳近くの殺生石、遊行柳、雲巌寺を巡った。
この鳴子温泉3泊4日はその前に決めていたから、こちらが7月の旅本番である。 |
|
7月25日(日)、11時過ぎに東京駅で東北新幹線に乗り、2時間少々で古川駅に着いた。仙台の一つ先である。
駅前にホテルのバスが待機しており、約1時間で「鳴子湯の里 幸雲閣」着。洋風の館がくすんだ田舎の景色にミスマッチだった。このホテルに3連泊して、4日間の自由行動だ。 |
| …………………… |
| 鳴子のこけし |
|
 |
|
こけしは、Wikipediaによれば、「江戸時代末期から、東北地方の温泉地において湯治客に土産物として売られるようになったろくろ引きの木製の人形玩具」。
伝統こけしは産地によって10系統あるようで、何年か前山形の肘折温泉で鈴木工房のご主人にいろいろ教わった。 |
|
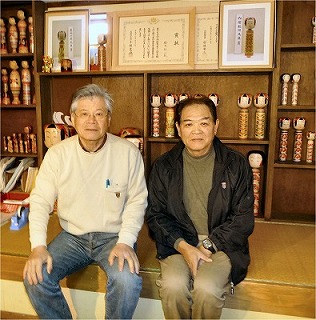 |
| 鈴木征一氏と(2008.12) |
|
鳴子温泉の鳴子系は、「首が回るのが特徴。首を回すと「キュッキュ、キュッキュ」と音がする。胴体は中ほどが細くなっていて、極端化すれば凹レンズのような胴体を持つ。胴体には菊の花を描くのが通常である。」(Wikipedia)
初日夜、ホテル内で菅原工房の製作実演があり、たっぷり見物した。 |
|
 |
|
 |
|
| 翌二日目、尿前の関への行き帰り、途中の菅原工房に立ち寄った。実演者の父であるご主人(菅原和平氏)と、茶をいただきながら長話となった。 |
|
 |
|
 |
|
| 尿前の関 |
|
 |
|
 |
|
| 南部道遙かにみやりて、岩手の里に泊る。小黒崎・みづの小嶋を過ぎて、なるごの湯より尿前の関にかゝりて、出羽の国に越えんとす。此の路旅人稀なる所なれば、関守にあやしめられて、漸(やうやう)として関をこす。大山(たいざん)をのぼって日既に暮れければ、封人(ほうじん)の家を見かけて舎(やどり)を求む。三日風雨あれて、よしなき山中に逗留す。 |
|
| 蚤虱馬の尿する枕もと |
|
|
|
 |
|
| あるじの云ふ、是より出羽の国に大山を隔てて道さだかならざれば、道しるべの人を頼みて越ゆべきよしを申す。「さらば」と云ひて人を頼み侍れば、究竟(くっきょう)の若者、反脇指(そりわきざし)をよこたえ、樫の杖を携へて、我々が先に立ちて行く。けふこそ必ずあやうきめにもあふべき日なれと辛き思ひをなして後(うしろ)について行く。あるじの云ふにたがはず、高山森々として一鳥声きかず、木の下闇茂りあひて、夜る行くがごとし。雲端につちふる心地して、篠の中踏分け踏分け、水をわたり岩に躓(つまづ)いて、肌につめたき汗を流して、最上の庄に出づ。かの案内せしおのこの云ふやう、「此のみち必ず不用の事有り。恙(つつが)なうをくりまいらせて仕合せしたり」と、よろこびてわかれぬ。跡に聞きてさへ胸とゞろくのみ也。 |
|
|
| 鳴子峡 |
|
 |
|
 |
|
| 紅葉の季節に賑わうという鳴子峡は、尿前の関近くから入って、途中の通せんぼで引き返さざるを得なかった。渓流の瑞々しさ、森の景色、山の滴(したた)り……、結構癒やされた。 |
|
| 鳴子温泉駅周辺 |
|
 |
|
| 駅前周辺が町の繁華街のようだ。三日目はこのあたりを当てもなくぶらぶらした。 |
|
 |
|
 |
|
 |
| ………………………… |
|
|
|
この5月は古希(70歳)の誕生日だった。
親族に祝ってもらったが、そのときの写真。 |
|
|
|
|
| Close 閉じる |
|
|