|
落語「芝浜」は三代目桂三木助(1903〜1961)の十八番(おはこ)だ。
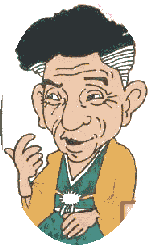 三代目三木助と言えば、声がか細いせいか地味で、胸にズシンとこない。一方、とぼけたところもあり、上品な感じもする。 三代目三木助と言えば、声がか細いせいか地味で、胸にズシンとこない。一方、とぼけたところもあり、上品な感じもする。
取りたてて印象に残る噺家ではない、と言っては失礼にあたるだろう。
しかし、五代目古今亭志ん生や六代目三遊亭圓生、八代目桂文楽のような、出し物よりも名前が有名な師匠には並ぶべくもない。
「芝浜」以外の出し物では「へっつい幽霊」、「崇徳院」、「三井の大黒」……。結構面白いが、取り立てて凄い、と興奮するほどのものでもない。
「芝浜」は違う。
彼の持ち味がにじみ出てくる。どのカセットやCDのシリーズにも、「三木助といえばこれ」ということで必ずあるから、いろんなときのいろんな寄席でのライブ録音を楽しむことができる。それぞれの録音で少しずつマクラや言い回しを変えている。しかし、どれをとってもこの出し物だけはたっぷり聞かせてくれる。失望させない。
三木助は昭和36年に亡くなった。その直後のさる寄席で、志ん生が三木助を偲んでこの「芝浜」を演じた。現在もカセットで味わえるのはありがたい。
この場合、志ん生のは彼に似合わずオーソドックスで、もしや三木助をたてたのではと勘ぐれるくらいに、「やはり芝浜は三木助」と納得させてくれる一席である。
「芝浜」のオチはさわやかだ。出来過ぎな気もするが、三木助調で、このように展開する。
大晦日。正月の用意も整った家で、魚勝こと、勝五郎と女房が除夜の鐘を聞きながら昔の苦労話をしている。女房が隠していた42両入りの革の財布を出し、
「夢じゃなかったんだよ、お前さん」
勝五郎はまだ「まさか」の顔だが、芝浜の波打ち際と、そこに漂(ただよ)っていた財布の紐の状景がおぼろげに浮かんでくる。
「しかし、あのときおめえは夢だと……」
あのままだと勝五郎の酒浸りは続き、拾った金を使ったことがわかると罪にも問われかねない。そこで大家に相談し、金は奉行所へ届け出て、勝五郎には「夢」を押し通した。
金は落とし主が出ず、戻ってきたが、それでも今日までずっと心を鬼にして黙っていた。
女房は涙ながらにうち明ける。
「もうお酒をお飲みになっても大丈夫と思って……」
勝五郎の感謝にほっとした女房が温めた酒を酌する。勝五郎、嬉しそうに口元まで運ぶが、思いとどまる。
「やっぱりよそう。また夢になる」
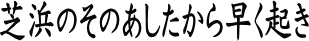
三木助がよく色紙などに書いた句だそうである。
|