|
浅草演芸ホール
昼の部は11時に開演していた。半分過ぎての途中入場だが、かまわず先輩は当日券を4人分買う。係りが素早く、横っちょの非常口に案内する。
立錐の余地なしとはこういうことだろう。2時から4時半まで、昼の部後半を狭い右サイドでずっと棒立ち、直立不動の見物だった。
寄席で満員とは?! 新聞販売所の招待客が多いとか、お盆だからとか……あれこれ思い描いたが、最大の理由は〝古今亭志ん朝追善、吉例納涼住吉踊り〟。そう、客みんなのお目当ては、住吉踊りだった。
ではあれ、この異常な混みようだ。ぼく同様に息苦しい棒立ちを強いられているご老体が心配である。「残念だけど帰ろうか」のお声がいつかかるかと、じっと横目で伺っていた。
寄席は三遊亭小円歌(女性)の三味線漫談がはじまるところだった。小円歌がよかった。
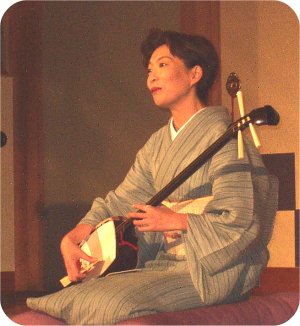
そのあと五街道雲助(落語)、三遊亭圓彌(落語)、あしたひろし・順子(漫才)、古今亭圓菊(落語)と続く。
3時に仲入りがあって、古今亭志ん橋(落語)、翁家和楽・小楽・和助(曲芸)。取りは三遊亭金馬(落語)。
通していずれも小話程度だが、熱がこもっていた。やはり金馬。軽いタッチで貫禄がある。あとの出番でも、ボケ・ズッコケに味わいがあった。
緞帳(どんちょう)が下りてしばし、にぎやかな出囃子で大喜利の幕が開く。
昼の部出演者総動員。「志ん朝師匠は心で偲ぶとして」との前口上で、吉例納涼住吉踊りがはじまる。
♪♪お伊勢ナー戻りにこの子が出来て
ハーヨイヨイお名を付けましょうヤンレ
伊勢松とハアーヤアトコセーヨイヤナ
アリャリャコレワイナこのなんでもセエーエーエー♪♪
(伊勢音頭)
♪♪吃(どもり)の叉兵書いたる絵紙性根が通い
皆抜け出たオイお若衆鷹を据え
ハアコリャコリャ塗笠女形の藤娘
座頭の下帯を犬が喰わえたらびっくり仰天し
杖を捜してヤッシッシハアコリャコリャ
荒儀の鬼が発起して鐘コラショ撞木
瓢箪で鯰を押さえましょ奴さんの行列
吊鐘弁慶矢の根の五郎♪♪
(吃叉)
♪♪エー奴さんどちら行く旦那お迎えに
さても寒いのに供揃い雪のせ降る夜も風の夜も
サテお供はつらいね何時も奴さんは高端折
アリャセコリャセそれもそうかいなあーエ♪♪
(奴さん)
♪♪エー姐さんほんかいなハアコリャコリャ
こぬぎぬの言葉も交わさず明日の夜は
裏のセ窓には私独りサテ合図はよいか
首尾をようして逢いに来たわいなアリャセコリャサ
それもそうかいなエハアコリャコリャ♪♪
(姉さん)
♪♪綱は上意を蒙りて羅生門にぞつきにける
時折しも雨風はげしき後ろより兜の錣を引っ掴み
引き戻さんとエイと引く綱も聞えし強者にて
彼の曲者に諸手を掛け
よしゃれ放しゃれ錣が切れる錣切れるはいといはせぬが
只今結うた鬢の毛が損じるはもつれるは七つ過ぎには
往かねばならぬ何処へ往かんとすか此方気にかかる
誰じゃ誰じゃ鬼じゃないものわしじゃないもの
兜も錣もらっちも要らないさあさ持ってけ背負ってけ♪♪
(綱上)
ここでハワイアン音楽が飛び入り。志ん朝師匠のテープ「小さな竹の橋・替え歌」に合せて女性群がフラダンスの乱舞。
♪♪さつまさアこりゃささつまさと急いで押せばエー
汐がさアこりゃさそこりて櫓が立たぬエー
猪牙でサッサ行くのは深川通い
渡る桟橋をアレワイサノサいそいそと
客の心は上の空飛んで行きたいアレワイサノサ主の傍
駕籠でホイホイ行くのは吉原通い
おりる衣紋坂アレワイサノサいそいそと
大門口を眺むれば深い馴染みのアレワイサノサお楽しみ
坊様ハイハイ二人で葭町通い上がるお茶やは
アレワイサノサいそいそと
隣座敷は大ようきさえつおさえつアレワイサノサ狐拳♪♪
(さつまさ)
目まぐるしく舞台は入れ替わり、興奮のボルテージが上がっていく。頂点は言わずと知れた「かっぽれ」。紀伊国屋文左衛門に「私しゃ貴男にかっぽれた」。
♪♪沖の暗いのに白帆が見ゆるヨイトコラセ
あれは紀伊の国ヤレコノコレワイノサヨイトサッササ
蜜柑船じゃえさて蜜柑船蜜柑船じゃえサア見ゆる
サテヨイトコラセあれは紀伊の国ヤレコノコレワイノサ
ヨイトサッササ蜜柑船じゃえ♪♪
満員を超す客席が興奮の坩堝と化す大団円だった。
みんな踊りのプロでもあった。「本物の踊りは歌舞伎座か、○○へどうぞ」とのたもうたが、"本物"だった。加えてすべてコミカル。笑いながら「スゴイ!」と言わざるを得なかった。
「よかったでしょう!」
大先輩も喜びと満足そのものだ。そう言いながら、涼しげに、すたすたと出口をあとにする。なんたるタフネス。
|